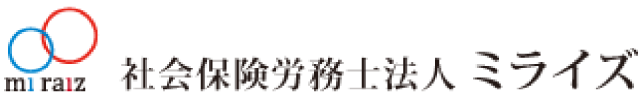社会保険手続き・給与計算
社会保険手続き
従業員の採用から退職までに発生する様々な手続き業務を代行いたします。
こんなときはご相談ください
- 手続きのやり方、書類の書き方が煩雑でよく分からない
- 日常の業務が忙しく、複雑な書類作成をする時間がない
- 手続きを外注化して、本業に集中したい
- 年金事務所から算定基礎届が届いたが、どうしたらいいか分からない
- 労働局から労働保険料申告書が届いたが、どうしたらいいか分からない
- 社会保険の月額変更の手続きの仕方が分からない

ミライズなら専門スタッフが社会保険手続きを代行

人手不足の中小企業では、専門の担当者を置くことも難しい場合があり、経営者自ら従業員の保険手続きを行っているケースがあります。手続きの過程で発生するミスや遅延は後々大きな損害をもたらすことにもつながりかねません。社労士に手続きを任せれば、リスク回避と業務効率向上の両面で大きな利点がもたらされます。
ミライズは部門ごとにスタッフを配置し、専門スタッフが手続きにあたりますので頻繁に行われる法改正にも迅速に対応いたします。
主な対応手続き
- 入社時手続き
-
- 雇用保険の加入
- 健康保険・厚生年金の加入
- 家族の扶養加入手続き
- 退職時手続き
-
- 雇用保険喪失
- 離職証明書発行
- 健康保険・厚生年金の喪失
- その他の主な手続き
-
- 月額変更届
- 高年齢雇用継続給付金
- 傷病手当金
- 通勤災害にかかる請求
- 出産手当金
- 労働災害にかかる請求
- 育児休業給付金
- 年度更新・算定基礎届
- 労働保険料の年度更新(申告・納付)、社会保険料決定のための手続き(算定基礎届)は毎年必ず行う手続きとなります。賃金台帳や出勤簿などの情報をもとに書類を作成、届け出を代行いたします。
顧問契約先との社会保険手続きの流れ
※新規クライアントの場合
- 顧問先様または
前社労士 - ミライズ
- 顧問先様
- 手続に必要な情報の受け渡し
- データ・書類の確認
- データのシステムへの入力・確認
- 各種届書作成・電子申請
- 届出・通知(控え)受領
- 完了・納品
- 届出書控えの受領・保管
- 保険証・離職票等の受領
給与計算
給与・賞与計算、明細発行、年末調整まで代行いたします。
※従業員100名程度まで
こんなときはご相談ください
- 給与担当者が退職または休職予定
- 社員数が増えてきたので、そろそろ外注したい
- クラウド勤怠システムを導入したい
- 紙の明細をやめて、クラウド給与システムを導入したい
- 複雑な給与計算を外注して、本業に集中したい

ミライズならクラウドシステム導入で切り替えもスムーズ



給与計算は、労働法、労働保険、社会保険、税法などのさまざまな法律をもとに行う必要があります。近年は、未払い残業などの訴訟のリスクなども高まっており法的根拠に基づいた給与計算を行わなければなりません。将来的にはAIやITシステムのさらなる普及で、簡素化される可能性がありますが現状ではまだまだ、手間や時間がかかる作業です。これらの手続きを経営者自ら行い続けることは、会社のためになりませんし、外注することで、営業やマーケティングなどの仕事に時間を充てることができます。
ミライズは「マネーフォワード」というクラウドシステムで給与計算業務を行っています。新たに社労士を切り替える場合でも、給与の仮計算、データの突合を行いながら、スムーズに移行できるためのシステムを構築しています。
給与計算代行の流れ
- 顧問先様または
前社労士 - ミライズ
- 顧問先様
- 給与計算に必要な情報の受け渡し
- 書類・データの受取・内容確認
- 不明点・不足書類の確認
- 給与システムへの入力・設定・確認
- 給与計算・仮計算
- 保管現状の給与データと突合・確認
- 翌月の給与計算・データ受領
- 完了・納品
就業規則作成・改訂
社内ルールを整備することで会社を守り、社員が働きやすい環境をつくることができます。

社内ルールの整備は会社経営に欠かせないことのひとつです。しかし、インターネットで入手した無料の規則のひな型では、会社を守り、発展させることはできません。法人設立時や社員数の増加による新規作成はもちろん、短時間勤務やリモートワーク導入などによる規則の改訂も経験豊富なミライズにお任せください。就業規則を整備することで、起こりうる問題への心配を解消し、社員が働きやすい環境をつくることができます。また、就業規則に関連・付随する賃金規定・育児介護休業規定作成なども対応可能です。
職場のルールブックのご案内
職場のルールブックとは
就業規則をもとに、職場内のルールやルールに込めた経営者の思い・考えをわかりやすく、より具体的に表現し、小冊子にまとめたものです。職場のルールブックには、就業規則に定められている規定がわかりやすい言葉やイメージで表現されています。
ルールだけではなく、経営理念などの経営者の思いも一緒に従業員の皆さまに伝えることができます。
ご紹介できるルールブック
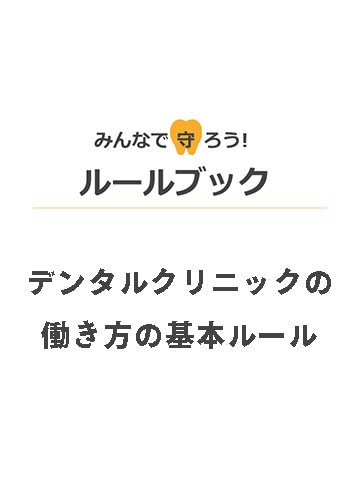
歯科、デンタルクリニック働き方の基本ルール
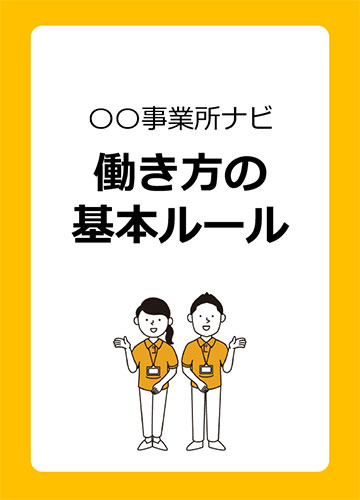
介護事業所働き方の基本ルール
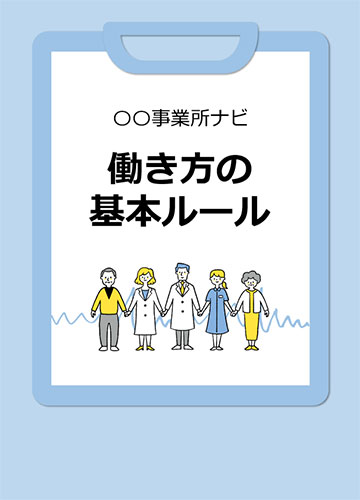
医療業界働き方の基本ルール
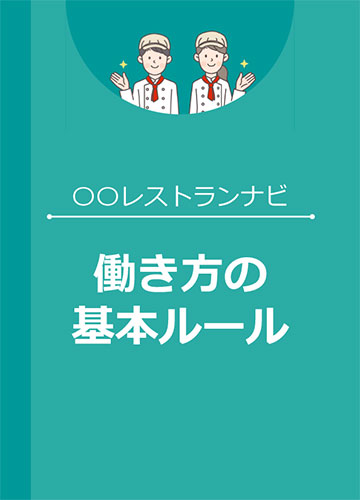
飲食店働き方の基本ルール

保育園働き方の基本ルール
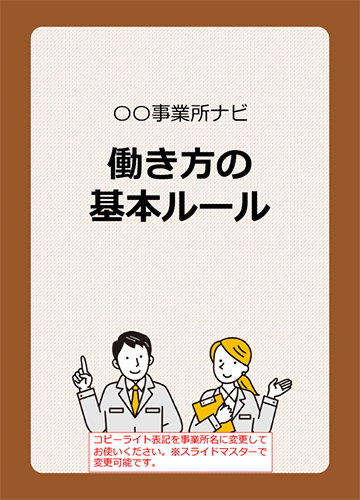
建設業界働き方の基本ルール

製造業界働き方の基本ルール
ミライズでは、業種別のルールブックをご提供しております。クライアントのリクエストに応じて、様々な労働環境に合わせたルールブックを作成しますので、お気軽にお問い合わせください。
人事労務相談
労務トラブルの予防と適切な対策を取ることで、企業経営リスクを回避します。
行政からの突然の連絡にも、スピーディーに対処します

労働トラブルは近年急増しています。社員の問題行動や発言、懲戒処分や解雇、未払い残業に対するリスクなど企業を取り巻く労務環境は時代とともに一段と厳しくなっています。未払い残業の請求権の時効も3年に延長され、さらには5年に延長される見込みもあり、労務課題に対してしっかり取り組まなければ、企業経営にとって大きなリスクとなるでしょう。問題が発生してしまってからでは、対応が取りにくくなるため、事前にチェックしてトラブルを予防することが重要です。就業規則、賃金規程、労働条件通知書、変形労働時間制、みなし労働時間制、固定残業代、休職規程、服務規律、テレワーク規程など定期的かつ包括的に様々な見直しが必要となります。また、問題社員などの対応で懲戒処分を行う場合の手続きや段取りは、より慎重に行う必要がありますので、その際はご相談ください。
行政対応
労働基準監督署の調査や年金事務所の調査など、対応をサポートをいたします。
行政からの突然の連絡にも、スピーディーに対処します

突然の労働基準監督署からの連絡、初めての年金事務所の調査、いったい何を準備すればいいのか焦ってしまいますよね。ミライズでは、行政からの連絡を受けた後、時間が限られている中でもスピーディーに対処し、対応方法を見極めます。
是正勧告書や指導書が届いた場合の回答方法もご相談ください。
企業型確定拠出年金導入
企業型確定拠出年金を導入することで、企業の負担を減らすことができます
代表者1名から加入できます

企業型確定拠出年金とは、所属する企業があらかじめ決まった掛金を拠出し、運用することで、将来の年金を受け取ることができる制度です。代表者あるいは役員の方であれば、有利かつ安心して加入できる可能性が高いため、ミライズでは導入をおすすめしています。
拠出限度額 660,000円(加入者一人あたり年額)
事業主が負担する掛け金は全額損金となります。
- 有利な理由
-
- Point1掛金は全額が法人の経費
- Point2個人は受け取るまで非課税(所得税法施行令第64条)
- Point3一時金の受け取りは、退職所得として分離課税(60歳で受給権を取得し、在職中も退職所得として受給することが可能)
- 安心の理由
-
- Point1確定拠出年金の口座内の資産は個人に帰属します。
- Point2みずほ信託銀行が年金資産を分別管理します。
- Point3投資信託のほか、銀行の定期預金でも運用できます。(貯金はペイオフが適用、銀行あたり1千万と利息相当を保証)
- 企業型の実施に関しては、厚生年金の適用事業者であることが条件となります。
- 制度の導入には厚生労働省への申請、承認が必要です。
- 企業型は運営管理手数料のほか、所定の手数料がかかります。
- 新規の加入者は原則70歳未満であることが条件となります。
初回ご相談無料
お問い合わせ・ご相談は
こちらから
初回のご相談は無料です。
人事労務・助成金申請等でお困り事がございましたらお気軽にご連絡ください。
全国からZoomを利用した
オンライン相談も可能です。助成金のサポートは顧問契約(労務顧問、手続顧問)が必要です。
-
お電話でのお問い合わせ
03-6907-3897【営業時間】平日 10:00~18:00
-
お問い合わせフォーム
メールでのお問い合わせ24時間受付中