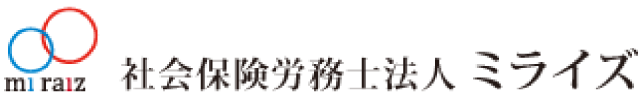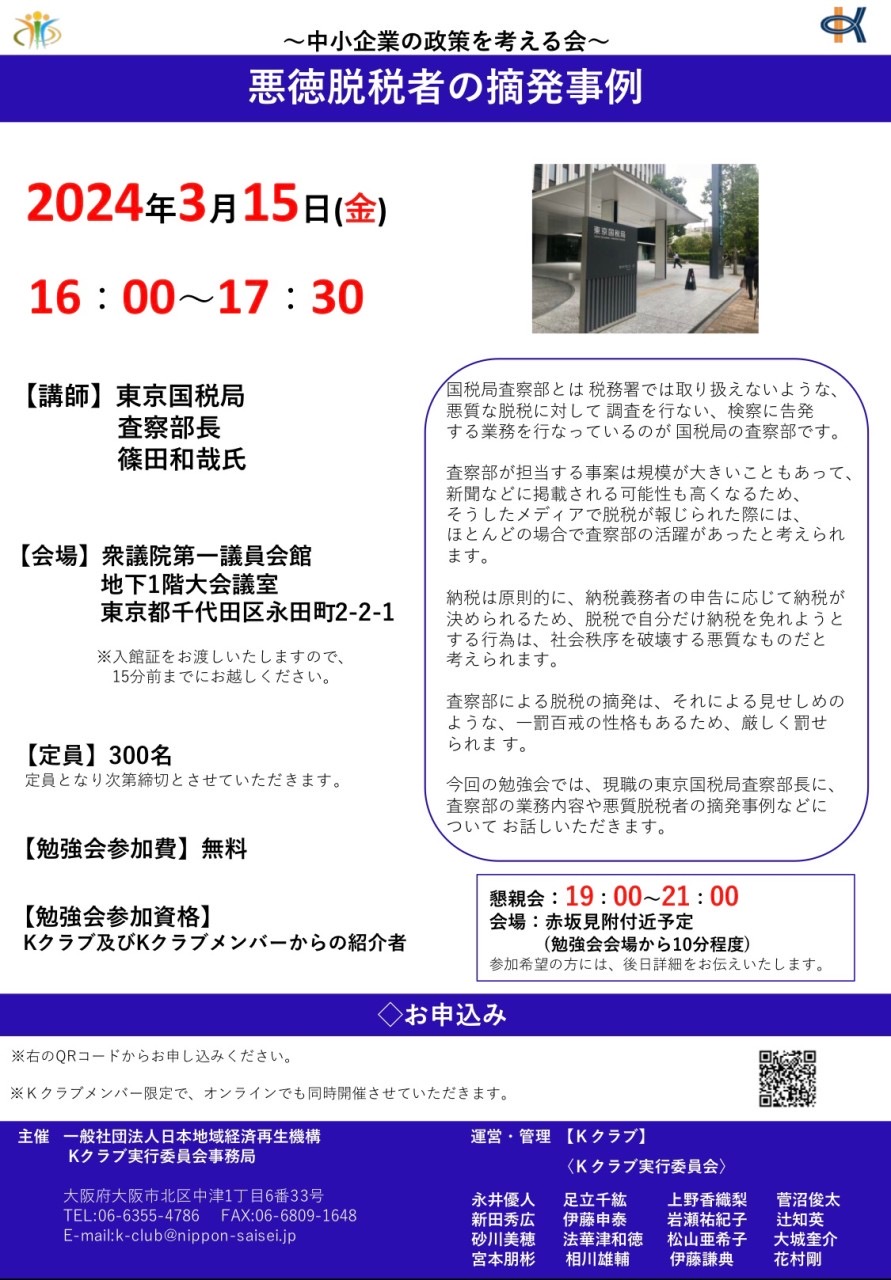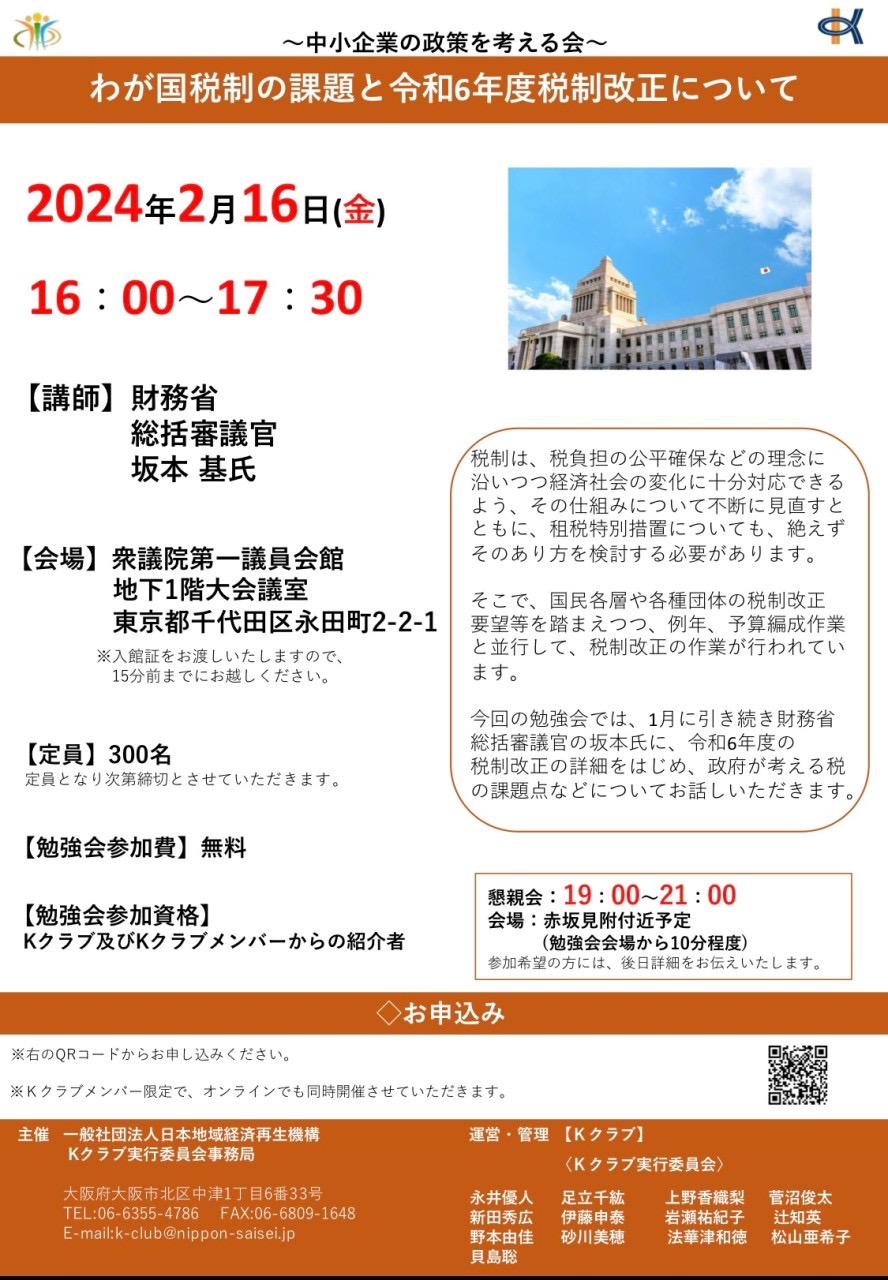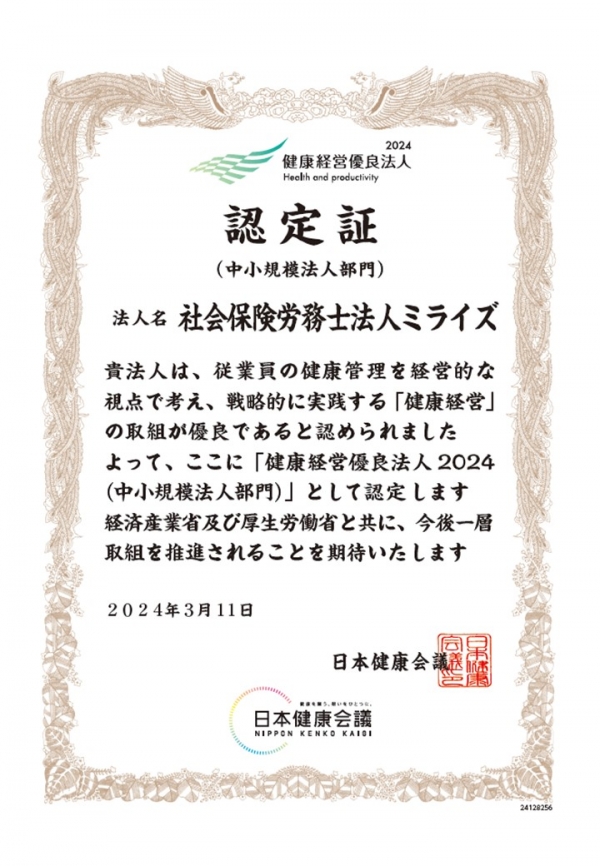新着情報
初回ご相談無料
お問い合わせ・ご相談は
こちらから
初回のご相談は無料です。
人事労務・助成金申請等でお困り事がございましたらお気軽にご連絡ください。
全国からZoomを利用した
オンライン相談も可能です。助成金のサポートは顧問契約(労務顧問、手続顧問)が必要です。
-
お電話でのお問い合わせ
03-6907-3897【営業時間】平日 10:00~18:00
-
お問い合わせフォーム
メールでのお問い合わせ24時間受付中